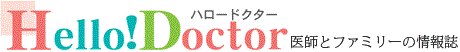富田林寺内町

大阪府の南東部・南河内と称される地域がある。
大阪府に居ながら、一度もゆっくり訪れたことがなかったのだが、チャンスがあっていくことになり、北摂から、高速を使うと1時間余りで到着。田園畑が周辺に広がる、山に囲まれた静かな中にも活気のある街があった。歴史的ないわれも多く、一度は是非、訪れてみるのべきで、この機会を与えていただいた方に感謝します。

国の「重要伝統的建造物群保存地区」および、旧建設省選定の「日本の道100選」のひとつである「富田林寺内町(トンダバヤシジナイマチ)」がある。1997年(平成9年)10月に大阪府で唯一、国の「重要伝統的建造物群保存地区」として選定されている江戸時代から昭和初期の町並みが残ることで知られる。
東西に7本、南北に6本の街路で区画された東西約400メートル、南北約350メートルの楕円形に広がる周辺よりも一段高い台地上に、現在も多くの町屋が残り近世の町割りを残している。幅の広い土居や竹藪、南側の石川と面するところから境域とわかる。整然とした街路の両側には、河内風の白壁の土蔵や、格子造りのとても歴史を感じる美しい景観が残されています。
寺内町とは、永禄初年(1558年)に誕生した、真宗の寺院を中心に堀や土塁などで防御した宗教自治都市です。近隣四ケ村から8人の有力者を集めて八人衆の合議制のもとで、御坊を中心とした街づくりをおこなわれました。江戸時代には幕府の直轄地となり、石川の水運、東高野街道・千早街道が交差する陸運に恵まれた、商業の街として大いに発展をとげます。酒造業が盛んで、「富田林の酒屋の井戸は、底に黄金の水がわく」といわれ、たくさんの酒屋がありました。
文化の街としても発展

豊かな富と自由な気風で文化の街としても発展します。御坊では能や浄瑠璃が盛んに興行され、俳諧が町人の楽しみとなりました。寺内町には多くの町屋が現存していますが、特筆すべきは、旧杉山家住宅(重要文化財)で、一般後悔されています。モダニズム能舞台を模して造られた大床の間。茶室もあります。
旧杉山家住宅は、女流天才歌人・石上露子(ルビ:イシノウエツユコ) 本名、杉山タカ(孝子)。明治15年(1882)、旧家大地主の長女の宿命を持って誕生しました。豊かな感性と古いしがらみの間で、やがて文学・詩歌の世界に導かれていきます。
明治36年(1903)21歳の時、与謝野鉄幹・晶子が主宰する『明星』に短歌3首を寄稿します。石上露子は、タカのペンネームです。目覚めと挫折を繰り返しながら生きた「薄幸の麗人」は、今も人々に愛され続けています。