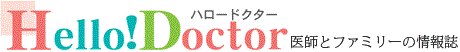接遇研修が生んだ好循環!
評価向上と集患増加の成功ストーリー

「医療はサービス業」という言葉が定着し、「患者さま」という呼び方も一般的になり医療現場においてもコミュニケーションについての知見が不可欠となりました。皆様の病院でも、患者満足度向上のため様々な工夫をされていることでしょう。
中でも「接遇」は単なる丁寧さではなく、「応対」と「処遇」を含むスキルとして、重要視されています。「接遇」と聞くと、ていねいな言葉遣いや立ち振る舞いといった「形」に目がいきがちですが、大切なのはそうした「形」の先にあるホスピタリティ行動をとれるようになることです。
今回は、一般社団法人医療接遇ホスピタリティ協会 代表理事 仲内真弓氏に医療現場における接遇の効果や必要性について事例を交えて語って頂きました。
医療接遇とは
医療機関は地域社会において欠かせない存在であり、経営の安定のためには、患者様からの信頼獲得が不可欠です。医療接遇は、その信頼獲得に大きく貢献する要素の一つです。受付対応、患者への声掛け、看護師の呼び出し方など、患者様との接点すべてにおいて、医療機関のイメージが左右されます。
医療における接遇とは、患者様に対する応対や受け答えの望ましいあり様のことで、言葉遣いや態度など、様々な要素を含みます。近年、医療従事者には患者様の気持ちを理解し、寄り添うホスピタリティ行動がますます求められています。どんな人が治療に関わるかで、治療の効果が変わってくることも分かってきました。
そのため、医療接遇では、患者様の意見を大切にし、良好な関係をいち早く築くためのスキルを学びます。「あいさつ」「おじぎ」といったコミュニケーションのための「型」は勿論、実習では実際の場面でどう話し、接すればすれば良いか指導を受け、さらに習慣化する方法を具体的に学びます。質の高いあいさつや言葉づかいを学び習慣化することは、患者様との信頼関係をいち早く築けるだけでなく、職場の雰囲気を良くするためにも大変重要です。笑顔一つで職場は劇的に変わるのです。
医療接遇を外部講師に依頼する3つのメリット
しかし、多くの医療従事者は、社会人として体系的な医療接遇を学ぶ機会に恵まれていません。患者様とのコミュニケーションで、言葉遣いや態度に悩み、周囲に相談しづらく、結果的に患者様にご迷惑をおかけしてしまうケースも少なくありません。実際の医療現場で直面する多様な状況に対応するための実践的なスキル習得が不足しているのが現状です。
近年、インターネット上の口コミサイトや院内への意見箱を通して、医療接遇に関する不満が数多く寄せられるようになってきました。また、他業種から医療機関に転職した管理職の方が、接遇の重要性を認識し、研修を導入するケースも増えています。このような状況下で、なぜ外部講師への依頼が有効なのでしょうか。主なメリットを3点ご紹介します。
メリット1
新規入職者への教育
新規入職者、特に受付スタッフは、患者様との最初の接点として、良好な関係構築が求められます。外部講師による研修では、笑顔、傾聴、共感といった基本的な接遇マナーから、医療機関特有のコミュニケーションスキルまで、ホスピタリティ行動を幅広く習得できます。これにより、高レベルの即戦力人材の育成が可能です。
メリット2
多角的な視点からの 改善支援
内部研修では気づきにくい、組織全体の雰囲気や個々のスタッフの潜在的な問題点を、外部の客観的な視点から見つけることができます。例えば、ストレスチェックやコミュニケーション分析など、多角的なアプローチにより、より深いレベルでの改善策を提案します。また、他の医療機関での事例紹介や、最新の接遇トレンドについても情報提供することで、組織の成長を後押しします。
メリット3
組織全体のスキルアップと継続的な成長
外部講師は、研修だけでなく、組織全体のスキルアップを目的としたコンサルティングやフォローアップも実施できます。これにより、ノウハウの属人化を防ぎ、組織全体で高いレベルの医療接遇を維持することができます。また、外部講師との継続的な関係構築を通じて、組織の成長に合わせた柔軟な対応も可能です。
医療接遇スキルの獲得で
離れた患者を呼び戻し、評判を回復
では、医療接遇の習得には具体的にどんなメリットがあるのでしょうか?とある産科病院の事例を通じてその具体例をご紹介します。ここでは、助産師をはじめとするスタッフの年齢層が20代から70代と幅広く、世代間の価値観やコミュニケーションスタイルの差異が顕著に見られました。特に、高齢のスタッフによる妊産婦様への対応に関する問題が複数報告され、患者離れに繋がっていました。
近年の妊産婦様は、WEBで病院情報を積極的に収集し、口コミや評価を参考に医療機関を選択する傾向にあります。この病院では、一部のスタッフによる「〜しなさい」「〜するのは当たり前でしょ」といった威圧的な言葉遣いや、患者様の質問に対して不親切な対応など、接遇面での問題が複数投稿されていました。これらのネガティブな情報が拡散された結果、病院の評判が低下し、新規患者の獲得が難しくなるという事態に陥っていました。
具体的には、以下のような事例が報告されました。
① 初めての妊婦検診で不安を抱えている妊婦様に対して、丁寧な説明が不足していた。
② 出産中に痛みを訴えている妊婦様に対して、適切な声掛けや安産のためのサポートが不足していた。
③ 退院後の育児に関する質問に対して、上から目線で回答されたと感じた。
これらの問題は、高齢のスタッフに限らず、組織全体のコミュニケーション不足や、患者様に対する意識の低さなどが複合的に影響していると考えられます。この状況を回復するため約2年間の継続的な医療接遇研修を実施した結果、スタッフの意識改革が進み、妊産婦様からのインターネット上の評価が向上しました。複数回にわたる実践的な演習を通じ、課題を具体化したうえで個々のスタッフに合わせた指導を行いました。特に、「若い妊産婦様から厳しい意見を頂いている」という事実を個別面談で共有することで、各スタッフが現状を深刻に捉え、改善に向けて主体的に行動するようになりました。この取り組みを通じ、スタッフは患者様とのコミュニケーションの重要性を再認識し、より丁寧で思いやりのある対応を心がけるようになりました。

患者様の治癒を促進する医療接遇を
私自身も現場で働いていた経験から、医療従事者の皆様が日々抱える課題や、患者様への想いを深く理解しております。各病院の課題に特化した、きめ細やかで結果の出る研修を提供できることが、弊会の強みだと自負しております。
医療スタッフの意識と行動の改革は、患者様のQOL向上に直結する重要な要素です。患者様中心の医療の実現に向けて、今後も一層尽力してまいりたいと考えております。
接客の実習風景