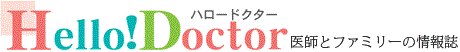全自動排泄処理ロボット
『マインレット 爽(さわやか)』が介護の世界を変える
<在宅におけるQOLの向上と介護労働負担の軽減にも>
田中 一正〈大和ハウス工業株式会社 理事 ヒューマン・ケア事業推進部長 ロボット事業推進室長 日本生活支援工学会
理事〉
「ロボット介護」の導入も次第に肯定的に

――生活支援ロボット、医療介護のロボットの展望はどうお考えですか。
田中 2013年度に経済産業省で、いろいろな安全基準が決まり、ようやく本格的にスタートしたところです。また同省では2035年には医療・介護の分野の生活支援ロボットで約5兆円の市場が生まれるという数字が示されています。
大和ハウスは2008年から販売をスタートし、現在でも実用レベルで市販されているのは大和ハウスが取り扱っている商品だけです。非常にいい評価をいただいています。
――ロボットに介護してもらうことに、抵抗感があるのではありませんか。
田中 確かに、「ロボット介護」というと「いや、ちょっと待ってよ」という人もおられます。ロボットと共生していくための、人間の心組みがまだまだできていない部分もあります。
しかし昨年9月の内閣府の調査データ「ロボットで介護をしてもらうということについてどう思うか」「介護するときにロボットを使いたいか」アンケートでは、両方とも60%という数字が示され、日本人が、ロボットを介護の世界に使う、導入することに次第に肯定的な方向に向かう数字が示されています。
「建築の工業化」を旗印にパイオニアメーカーとして歩んできた当社が、今後は「大和ハウスといえば介護ロボット」という、一部で定着しつつあるイメージが、さらに広まるように、頑張りたいと思っています。
――大和ハウスとしての、これからの課題はどこにおいておられますか。
田中 ユーザー本位の優れた製品を今後自社でも開発していかなければならないのは当然ですが、介護ロボットをはじめ、ロボット技術を使いこなす介護者が、これからどんどん求められていきます。その教育・研修が非常に大事になってきます。使いこなす人材の養成にも、さまざまな形で参画していく必要があると考えています。
――医師の先生方にメッセージを。
田中 医師の先生方に積極的に使っていただきたいと願っています。ロボット介護機器は国の定めるさまざまな保険の対象にはなっていませんし、安全基準もまだ決まっていないなど、ロボット自体のシステムも今後の改良の余地はあります。しかしそれだけに、いち早くお使いいただくことによって、医療機関のステータスも上がり、他の医療機関との差別化も図られ、介護・看護の労働負担軽減によって優れた人材が集まり、診療内容の高度化にもつながると、確信しています。
――ありがとうございました。
田中 一正 理事略歴
大和ハウス工業株式会社理事
ヒューマン・ケア事業推進部長
ロボット事業推進室長
医療・介護支援室 担当
〈略歴〉
1952年
滋賀県生まれ。
立命館大学理工学部土木工学科卒業。
1975年
大和ハウス工業株式会社入社。
滋賀特建営業所長、
東日本シルバーエイジ研究所長
西日本シルバーエイジ研究所長
総合技術研究所副所長を歴任。
シルバーエイジ研究所は、大和ハウス工業における医療・福祉分野の施設建設を専門に行うセクションとして1989年に設立。病院・老人保健施設・有料老人ホーム・グループホームなどのマーケティング、建設・運営の企画提案など幅広い実績がある。
また、大和ハウス工業における新規事業であるロボット事業を創業した。
2008年度経済産業省ロボット産業政策研究会委員。
著書には
「デイサービスセンターの開設・運営マニュアル(綜合ユニコム)」、
「北欧のノーマライゼーション(TOTO出版)」などがある。